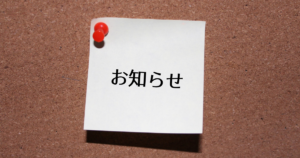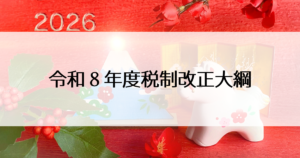ご相続の開始が近くなっていても検討できる節税対策10選

 ご相談者
ご相談者母親の容態が思わしくありません。こんな時なのですが、何か今からできる相続税対策はありますでしょうか?



お母様の状態によっては難しいこともありますが、意思能力がしっかりしていらっしゃったらいくつか検討できる事項はあります。
ご相続開始直前の節税対策の基本的な考え方
まず対策を行うには何よりもご本人様の意思能力があることが必要となります。
最近は長生きされる方が増えた半面、認知症の問題も出てきています。認知症と診断されると、売買や贈与等の契約行為が無効と判断される場合がありますので、注意が必要です。
次に、税務の観点から行きますと、相続税を支払いたくないためにいろいろと相続開始直前で対策を始めても、既にその抜け道はふさがれている場合もあります。例えば、暦年贈与で行きますと、相続開始前3年以内の相続人等に対する贈与は相続財産に持ち戻しをすることになっていますので、その間の贈与は相続税対策としての意味をなさなかったことになります。
ご相続の開始が近くなっていても検討できる節税対策10選
1.相続時精算課税制度による贈与
贈与の方法には大きく分けて暦年贈与と相続時精算課税制度による贈与の2つがあります。
このうち、前者の暦年贈与では前述のように相続開始前3年以内の贈与は相続財産に持ち戻す必要があります(令和6年1月1日以後の贈与からは随時7年以内に延長されます)。これはたとえ110万円以下で贈与税が非課税であっても同様です。
これに対して、後者の相続時精算課税制度による贈与では、年間110万円の非課税枠があるのは暦年贈与と同様なのですが、暦年贈与のように相続開始前3年以内の贈与の持ち戻す必要はありません(ただし、今後の税制改正には留意が必要です)。
つまり、相続が近い時期に行う贈与では、暦年贈与よりも相続時精算課税制度による贈与が有効になる場合があります。
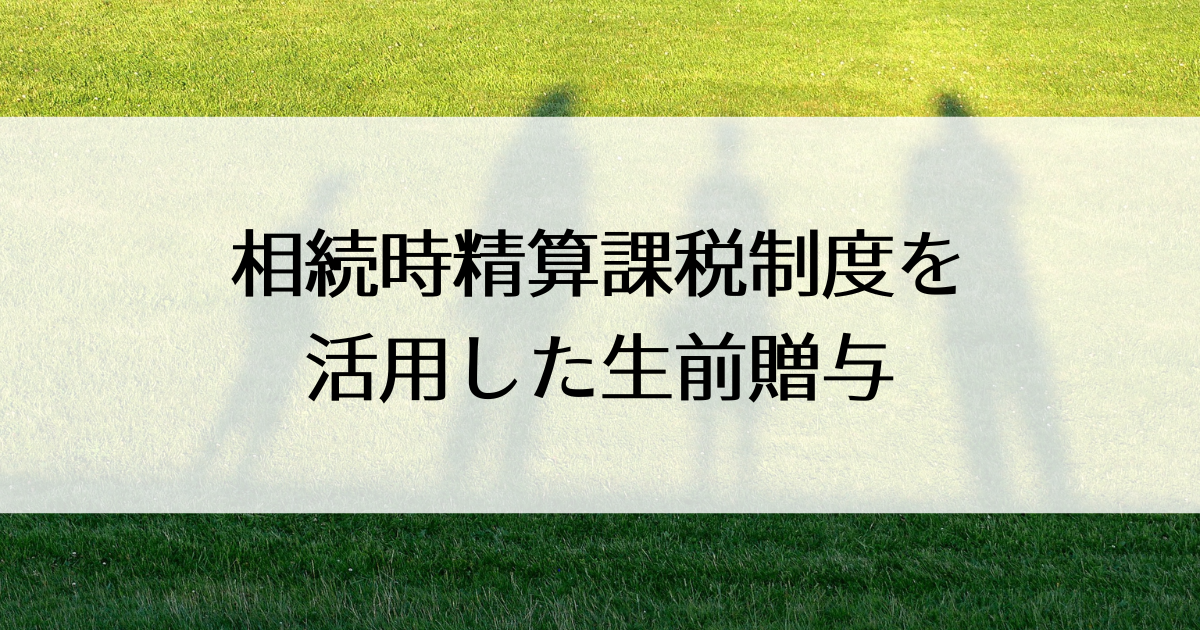
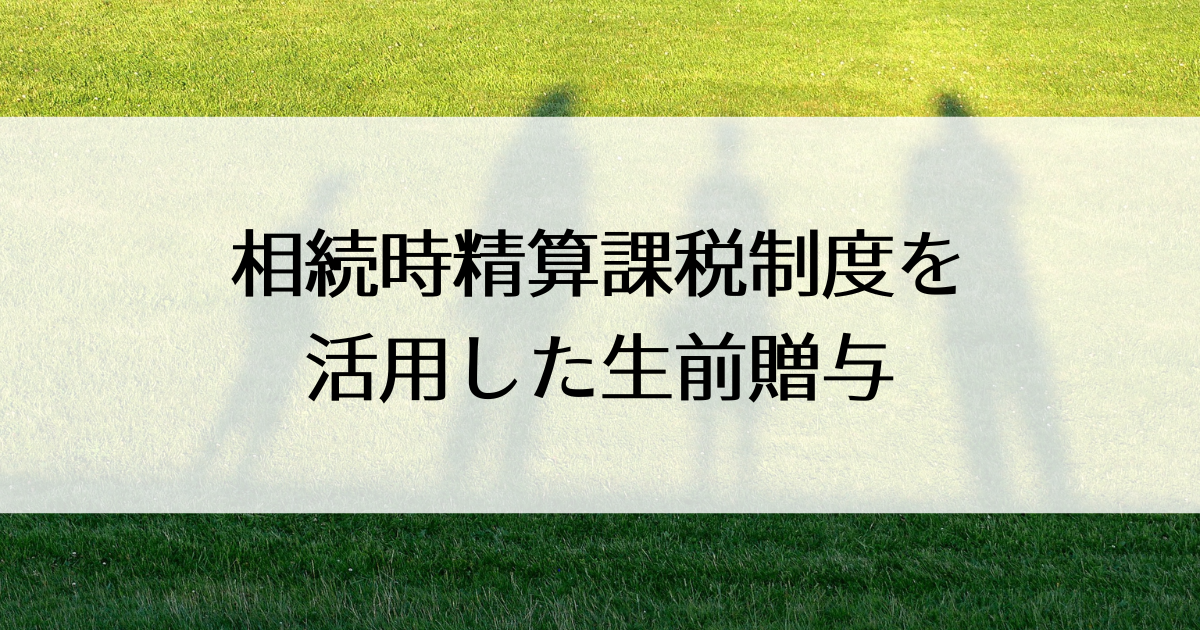
2.相続人、受遺者以外への贈与
上記の相続財産への持ち戻しとなる対象者は、「相続又は遺贈により財産を取得した者」(相法19①)となります。
すなわち、相続又は遺贈により財産を取得しなかった者、例えば孫への贈与などは相続財産へ持ち戻す必要はありません。
なお、「相続又は遺贈により財産を取得した者」となっていることから、例えばその相続で何も財産を取得しなかった相続人もたとえ相続開始前に贈与を受けていたとしても相続財産へ持ち戻す必要はありません。
3.生命保険の非課税枠の活用
預金で相続した場合には相続税がかかる場合でも、生命保険金に組み替えていれば500万円×法定相続人の数で計算された金額までは非課税となります。
そのため、お亡くなりになられる方が生命保険に加入されていなかったり、又は加入していても上記の非課税枠未満である場合はその差額まで一時払いの終身保険に加入することにより相続財産を減らせる場合があります。
なお、死亡退職金にも同じように500万円×法定相続人の数で計算された金額までは非課税となっています。非上場の会社の株主兼会社役員なら退職金の支払いによって株式の評価も減額できる可能性があることから検討の余地があると思われます。
4.養子縁組の活用
養子縁組により、実子がいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人まで法定相続人の数を増やすことができます。
相続税を計算する際の基礎控除額や生命保険金の非課税枠などが増加することになるため、相続財産の減少につながります。
この点、節税目的の養子縁組が裁判で争われたのですが、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない、との判断がなされています(平成29年1月31日最高裁判決)。
ただし、養子縁組により法定相続分が減少した相続人とトラブルになる事例などもあることから、事前に他の相続人に説明するなどの配慮が望まれるところです。
5.非課税資産の購入
例えば、墓地や仏壇仏具などは相続税が非課税とされていますので、ご生前にこれらを購入して支払い済みである場合は相続財産の減少につながります。
ただし、仏壇仏具等であっても商品、骨とう品又は投資の対象として所有するものはこれに含まれないとされていますので、留意が必要です。
6.非課税贈与の活用
例えば、①扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものや、②個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの、③いわゆる住宅取得等資金や教育資金、結婚子育てに係る贈与で一定の要件を満たすものについては贈与税がかからず、前述の相続財産への持ち戻しも不要とされています。
(ご参考:国税庁HP「贈与税がかからない場合」)
ただし、既に平成22年度税制改正により廃止されていますが、相続時精算課税適用者が住宅等取得資金の贈与について加味した住宅資金特別控除額(1,000万円又はその年分の贈与により取得した住宅取得等資金の額のうちいずれか低い額。旧措置法70の3の2)については持ち戻しが必要とされていますので留意が必要です。
7.小規模宅地等の特例の適用の検討
小規模宅地等の特例は、土地評価額の最大80%が減額できるものでできる限り活用したい制度になります。
例えば、お亡くなりになられる前にご自宅から施設へ移られている場合には、その施設が老人ホームなら老人福祉法等に規定する特別養護老人ホーム等であることなどの要件を満たす必要があるため、要件を満たすかどうかの確認を行っておくことも有用であると思われます。


8.実家のリフォームの検討
住むうえで必要な通常の維持修繕にかかる費用は、原則として相続財産にはならないと考えられます。そのため、可能であれば、必要な維持修繕はご相続の開始前に行うことが有用だと考えられます。
ただし、通常の維持修繕を超えた増改築等に当たる場合には、その増改築等に係る部分の再建築価額から課税時期までの間における償却費相当額を控除した価額の100分の70に相当する金額を加算した価額により評価する場合もあることから留意が必要です。
(ご参考:国税庁HP「増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」)
9.(賃貸)不動産購入の検討
不動産を購入することによる相続財産の減少に係る仕組みについては以下の記事をご参照いただけると幸いです。


ただし、相続開始の直前で節税目的のために不動産の購入などを行うと税務調査で否認された事例もありますので注意が必要です。
10.地積規模の大きな宅地の適用の検討
三大都市圏においては500㎡以上の宅地、三大都市圏以外では1,000㎡以上の宅地について一定の場合には土地の評価を大きく減額してもらえる地積規模の大きな宅地の評価というものがあります。
(ご参考:国税庁HP「地積規模の大きな宅地の評価」)
土地の評価は基本的に利用単位ごとに判定することになるため、もし可能であれば要件を満たすように利用単位を変更することが考えられます。
例えば、未利用地(三大都市圏で1,050㎡)に賃貸マンション2棟を建築予定である場合、基本的に利用単位は1棟ごとに判定することになるため、450㎡と600㎡で建築するよりは525㎡ずつで建築するほうが有利になる場合もありますので建築の際に考慮に入れられてみてはと思います。