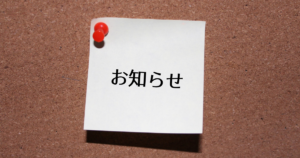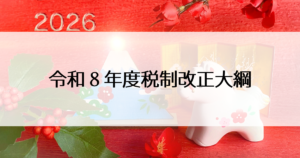二次相続を踏まえて一次相続で気を付けておきたいこと
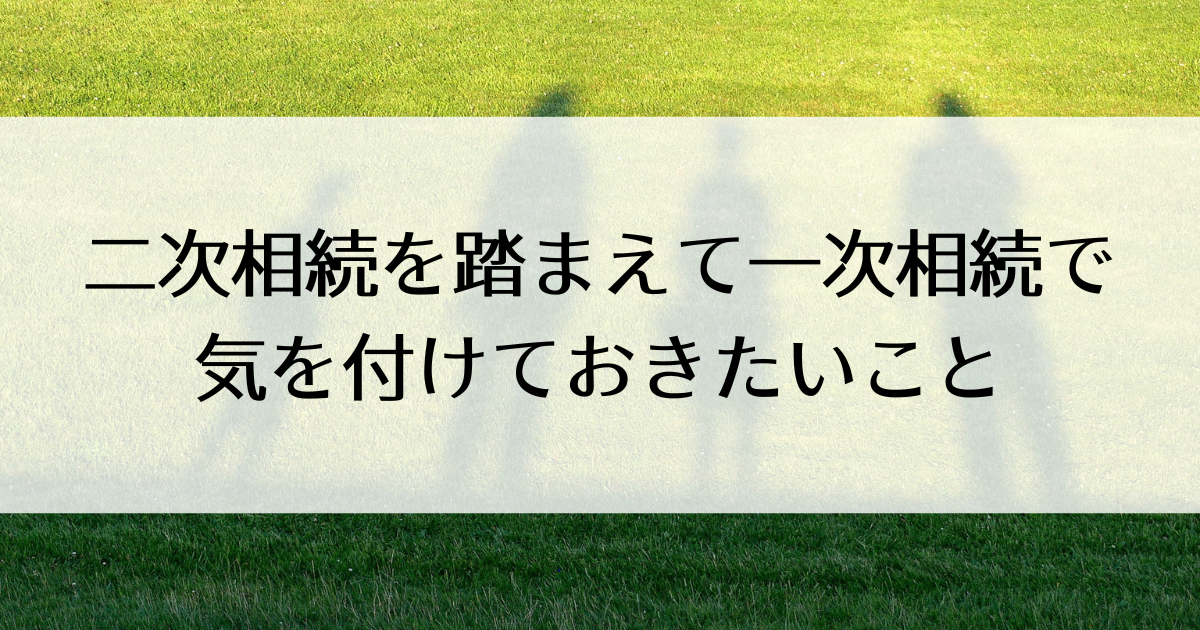
 ご相談者
ご相談者先日、父の相続が発生したのですが、母も体調が良くありません。二次相続を踏まえた一次相続の検討を行っておきたいのですが・・・



それは心配ですね。二次相続の特徴からご説明しましょう。
一次相続と二次相続
父又は母が亡くなった時の相続を一次相続と言い、続けて残りの母又は父が亡くなった時の相続を二次相続と言います。
一次相続では配偶者の税額軽減(配偶者控除)が使えるため、次の相続のことは置いておいてとりあえず母(父)にというケースもあると思われます。
しかし、ある程度の財産がある場合で相続税のことが気になる場合は、二次相続のことを踏まえたうえで一次相続の検討を行う方がよい場合もあります。
二次相続の主な特徴
1.法定相続人数が減少
もともと父、母、長男、長女の4人家族であることを前提にしますと、一次相続の法定相続人数は3人(母(父)、長男、長女)となります。
これが二次相続の法定相続人数は2人(長男、長女)になり、1人減少します。
法定相続人数が1人減少することにより、基礎控除額が600万円、生命保険の非課税枠が500万円減少するなど相続税の増加要因となります。


2.配偶者の税額軽減が使えない
1億6,000万円又は配偶者の法定相続分までは相続税がかからないのは、配偶者の特権であり、他の相続人は適用することができません。


3.小規模宅地等の特例の適用要件が厳しくなる
例えば、一次相続で配偶者がご自宅を相続されて小規模宅地等の特例を適用する場合、特に要件はありませんでした。
しかし、二次相続で小規模宅地等の特例を適用しようとする場合、同居親族や家なき子の要件を満たす必要があります。
同居親族
以下の両方の要件を満たしていること。
①相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住していること
②その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること
家なき子
以下のすべての要件を満たしていること。
①居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと
②被相続人に配偶者がいないこと
③相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと
④相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族または取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと
⑤相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと
⑥その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること


4.配偶者の固有財産も加算される
二次相続では一次相続の財産に加えて配偶者固有の財産が上乗せされるため、相続財産が増えやすい傾向にあります。
また、相続税は財産額が多くなるほど税率も高くなるため、適用される税率が上昇する可能性があります。
二次相続を踏まえて一次相続で検討しておきたいこと
まずは、一次相続での財産債務を洗い出すことが必要です。
次に、配偶者固有の財産も洗い出すことが可能でしたら、二次相続での相続税シミュレーションを行うことが有用です。このシミュレーションは一般の方では難しく、例えば一次相続では通常適用する配偶者の税額軽減をあえて適用しないことにより一次相続と二次相続の合計税額を少なくすることができる場合もあります。
もし二次相続での相続税シミュレーションの結果、ご希望される遺産分割案では二次相続で相続税が発生しそうな場合、小規模宅地等の特例の適用要件の充足を検討、生前贈与の検討、不動産の見直し(資産の組み換え)、生命保険への加入検討なども行ったほうがよいかもしれません。
税理士としてお伝えしたいこと
上記のように、税理士としては一次相続と二次相続を踏まえたご提案はさせていただくのですが、実際はお亡くなりになられた方と長年連れ添ってこられた配偶者のご意向を尊重すべきと考えます。
親としては、子どもが親の老後のことは棚に上げて税金のことばかり話しているのを聞かされるはうんざりしますし、もともとはご夫婦で築かれた財産なので、残された配偶者のご意見をしっかり聞くことが結果的に円満相続につながるものと理解しています。