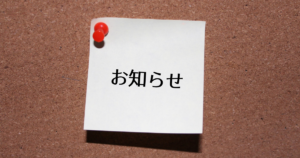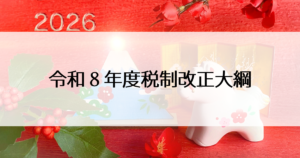遺言書と異なった遺産分割はできますか?

 相続人
相続人亡くなった父が遺言書を残していたのですが、相続人はこれとは異なる遺産分割を望んでいるのですが可能でしょうか?



遺言執行者がいるかどうかで対応が異なります
遺言書の目的と効力
遺言書を残さずにお亡くなりになられた場合、相続人全員で遺産分割協議を行うことが原則となります。
しかし、相続人間の仲が悪い場合や不動産のように平等に分けにくい財産の比率が高い場合など、争族になることを避けるためには遺言書で予め遺産をどのように引き継いでほしいと指定しておくと、相続人間の遺産分割協議を省略することが可能となります。この場合、付言事項と言ってお亡くなりになられた方が残された相続人に対する感謝の言葉やどうしてそのような遺産分割方法にしたかの説明があれば、より相続人の理解も得られやすい場合が多いと思われます。
他方で、遺言書を残されるご本人が税金について詳しいとは限らず、その遺産分割の内容だと例えば、配偶者の二次相続で不利になる可能性が高い場合や小規模宅地等の特例という土地の評価を減額できる規定が適用できない場合もあります。


また、親は子どものことを平等に可愛いと考えて、遺産分割は平等にと考えるケースが多いのですが、実際にはリストラや離婚、病気等その他子どもの置かれる状況によっては、子ども同士の間で相続割合を変えたいと考えるケースもあるかもしれません。
遺言書があっても遺産分割を行いたいというニーズがある場合、遺言執行者の有無によって対応が異なることになります。
遺言執行者がいない場合
遺言執行者がいない場合、相続人全員の同意があればその遺言内容と異なる遺産分割を行うことも可能です。
こうすることによって、前述の税務の問題を有利にしたり、援助の必要な相続人に多くを相続させる等が可能になります。
遺言執行者がいる場合
民法上、遺言執行者がいる場合には、相続人による遺言執行の妨害が禁止されています。
遺言執行者はお亡くなりになられた方の意思を尊重すべく、遺言の内容のとおりに執行することになるため、相続人がこれを妨害することはできないことになっています。
ただし、実務上は遺言者は既にお亡くなりになられており、残された相続人の全員が上記の事情等により遺言とは異なる内容で遺産分割を行いたいというニーズがあり、遺言執行者がこれに同意する場合は遺言内容と異なる遺産分割ができる場合があります。
遺言書は何度でも書き直すことは可能ですので、相続人の中に特に援助が必要な事情が生じた場合には書き直すことも必要となることもあるかと思われます。また、相続税がかかる場合などは税務の専門家にご相談されてから遺言書を書くのも有用ではないかと思われます。