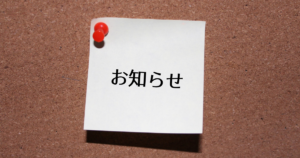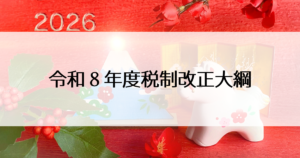相続時精算課税制度を活用した生前贈与
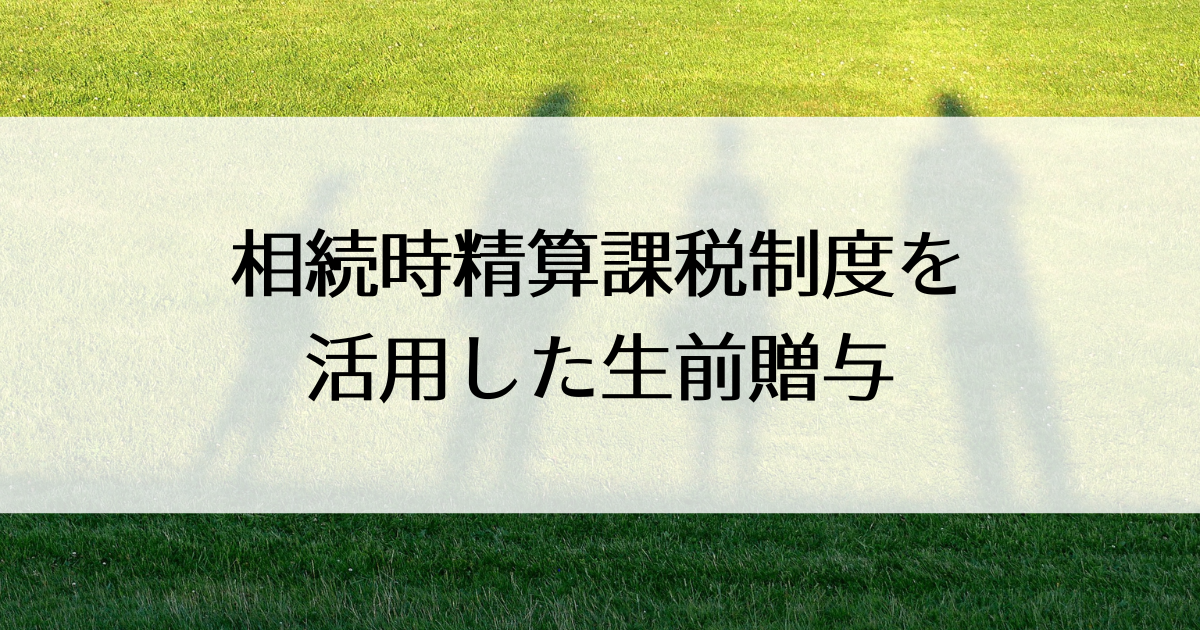
 ご相談者
ご相談者父は生前対策に協力的なのですが、相続開始の3年前までの贈与は相続財産に持ち戻しになると聞いたのですが・・・



暦年贈与はそうですね。ただし、最近は別の贈与を選択される方が増えています。
贈与の種類
主な贈与の方法としては①暦年贈与と②相続時精算課税による贈与の大きく2つがあります。
ご相談者が疑問に思われているように、暦年贈与による生前贈与の場合、例えば年間110万円未満で贈与税を申告する必要がなかったとしても相続開始3年前の贈与は相続財産に持ち戻して相続税の計算を行う必要があります。
税法では「課税の公平」が考え方の根底にあり、相続開始直前で対策を講じた人と講じなかった人との差を無くそうとしたためです。
なお、この「3年前」は税制改正がなされ、令和6年1月1日以降の暦年課税に係る贈与により取得した財産については、その加算対象期間が相続開始前7年以内と延長されました。
ただし、影響があるのは令和6年以降の贈与となるため、まるまる7年以内の贈与が持ち戻されるのは令和13年以降となります。
暦年課税と相続時精算課税
両者の主な比較は以下のとおりです。
| 相続時精算課税 | 暦年贈与 | |
|---|---|---|
| 贈与者 | 60歳以上の父母又は祖父母 | 制限なし |
| 受贈者 | 18歳以上の直系卑属である 推定相続人又は孫 | 制限なし |
| 基礎控除 | 年間110万円 | 年間110万円 |
| 特別控除 | 2,500万円 | なし |
| 贈与税率 | 2,500万円超は一律20% | 10~55%の累進課税 |
| 届出 | 相続時精算課税選択届出書 | 不要 |
| 相続財産への加算 | 基礎控除110万円を超える 適用を受けた過去の贈与すべて | 相続開始前3年間 (令和6年以降は順次7年間) |
現在は相続時精算課税と暦年贈与のいずれも基礎控除が年間110万円となっていますが、令和5年以前の相続時精算課税制度による贈与では基礎控除がなく、たとえ数万円であっても原則としては贈与の申告をすることになっていて使い勝手が悪く、同制度を選択する人が増えない状況でした。
これが税制改正により、相続時精算課税による贈与でも令和6年以降は年間110万円の基礎控除が設けられることになりました。
相続時精算課税の主なメリットとデメリット
相続時精算課税による贈与の主たるメリットは、相続開始3年前(順次7年前まで延長)の基礎控除以下の贈与であったとしても相続財産に持ち戻さなくてもよいということです。
この点、暦年贈与だと相続開始3年前(順次7年前まで延長)の贈与はたとえ基礎控除以下の贈与であったとしても相続財産へ持ち戻すことになるため、持ち戻された分については相続税の節税のために行っていた生前贈与の効果がなくなることになります。
ただし、デメリットとしては一度相続時精算課税制度を選択するとこれを撤回することはできません(暦年贈与に戻ることはできません)。
また、基礎控除以下であれば相続開始前3年以内であっても相続財産に持ち戻すことは不要ですが、基礎控除を超える分について何年前であっても相続財産に持ち戻すことが必要です(この点、暦年贈与であればいわゆる時効により贈与税申告は不要、かつ相続財産への持ち戻しも不要という可能性があります)。
さらに、税法は毎年改正があるため、相続時精算課税制度の使われ方によっては将来的に税制改正のリスクがあるため、少なくともこれらのデメリットがあることを踏まえて相続時精算課税制度を適用するか否かを検討することをおすすめします。