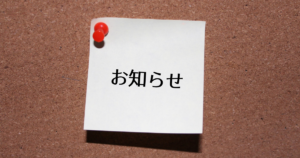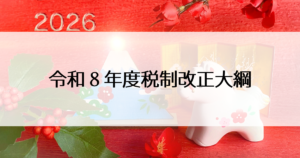知っておきたい!おひとりさまの相続

 ご相談者
ご相談者私には相続人がいません。高齢にもなってきたので、自分が亡くなった後のことが心配になり、できることはしておきたいと思います。



いわゆるおひとりさまの相続についてご説明しますね。
お一人様の相続
おひとりさまの相続とはお一人で暮らされている場合など配偶者、子、兄弟姉妹がいない場合の相続を言います。また、配偶者、子がおらず、兄弟姉妹はいたものの先に皆亡くなっており、関係が疎遠となった甥、姪がいる場合も事実上のおひとりさまの相続と言えるかもしれません。
それでは以下で法定相続人のご説明と法定相続人がいない場合のご説明をさせていただきます。
法定相続人
まず、お亡くなりになられた方の配偶者(夫、妻)が法定相続人となります。配偶者以外の法定相続人と法定相続割合は以下のとおりとなります。
第1順位 子ども
例:相続人が配偶者、長男、長女の3名の場合
法定相続割合は配偶者が1/2、残りの1/2を子の人数で按分することになるため、この例では配偶者1/2、長男1/4、長女1/4 となります。
なお、配偶者がおらず、子どもだけの場合は1を子の人数で按分することになるため、この例では長男1/2、長女1/2となります。
第2順位 親
例:相続人が配偶者、お亡くなりになられた方の父親、母親の3名の場合
法定相続割合は配偶者が2/3、残りの1/3を親の人数で按分することになるため、この例では配偶者2/3、被相続人の父親1/6、母親1/6となります。
なお、配偶者がおらず、親だけの場合は1を親の人数で按分することになるため、この例では父親1/2、母親1/2となります。
第3順位 兄弟姉妹
例:配偶者、お亡くなりになられた方の兄、妹の3名の場合
法定相続割合は配偶者が3/4、残りの1/4を兄弟姉妹の人数で按分することになるため、この例では配偶者 3/4、兄1/8、妹1/8となります。
なお、配偶者がおらず、兄弟姉妹だけの場合は1を兄弟姉妹の人数で按分することになるため、この例では兄1/2、妹1/2となります。
法定相続人がいない場合
配偶者、子、兄弟姉妹がいない場合、特別縁故者(内縁の妻など)が遺産を引き継ぐ場合があります。また、配偶者、子、兄弟姉妹がおらず、特別縁故者もいない場合で、不動産が共有になっている場合は共有者がその不動産の持分を引き継ぐ場合もあります。
配偶者、子、兄弟姉妹、特別縁故者、不動産の共有者がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属することになります。
おひとりさまの相続の問題点と一般的な対応策
例えば父親が亡くなった場合、配偶者や子どもでも父親の遺産や債務を正確に把握することは困難な場合があります。例えば、最近は通帳のない銀行預金が増えてきていますし、ビットコインなど実物がないものもあります。
また、スマホやパソコンなどのパスワードが分からなければ、それらを開くこともできません。
これが兄弟姉妹、甥、姪などになるとさらにお亡くなりになられた方との関係性が希薄なケースが多いため、さらに情報の収集が困難になるものと思われます。
これらの問題を回避するための対応策として、以下のようなことが考えられます。
1.終活を行う
やはり自分のことは自分自身が一番よく分かっているので、ご本人様ご自身で財産債務をまとめておくことが有用です。
また、残された者の手続きを簡素化するために、例えば、銀行預金や証券会社の口座などはできるだけ一つ、又は二つぐらいの口座にまとめて他の口座は解約しておくことなども考えられます。
あと、遺産内容やスマホ、パソコンなどのパスワードをまとめて一覧表に整理しておくことも有用だと考えられます。
2.遺言書を作成する
前述のように、法定相続人等がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属することになります。もし、生前にお世話になった方や団体、施設、友人などがいらっしゃる場合、それらの方は相続人とはなりませんが、遺贈という形で引き継いでもらうことは可能です。
また、配偶者や子がおらず、関係が疎遠な兄弟姉妹、甥、姪が相続人になる場合も遺贈を検討することもあります。
なお、遺言書には公正証書遺言や自筆証書遺言などの種類がありますが、遺言書は民法で定められた形式に従ったものでなければ無効となる可能性があるため、多少費用はかかっても公正証書遺言で作成されることをおすすめします。
なお、遺言書を作成する際には遺言の内容を適切に実行してもらえるように、信頼できる方を遺言執行者に選任しておくことも有用だと思われます。
3.任意後見契約を検討する
もしお亡くなりになられる前に認知症になるなど、一人では正常な判断ができなくなる場合に備えて財産管理等を任せる任意後見人を選任しておくことが考えられます。 任意後見人は友人や知人など信頼できる方がいらっしゃれば、その方にお願いするのが良いのではないかと思われます。
4.死後事務委任契約を検討する
通常、お亡くなりになられた後はご家族が死亡届の提出や葬儀の手配、各種事務手続きを行う場合が多いですが、おひとりさまの場合はそれらの手続きを行ってくれる方がいない場合が多いです。
そのため、死後の手続きを実行してもらえるように死後事務委任契約を検討する場合があります。